
Story フォルム70年のあゆみ
車両部品づくりは、日本の再生への貢献であった。
-
終戦から5年──。南麻布に町工場が誕生。
金型とプレスで “東洋の奇跡” の一翼を担う。自宅の空地に10坪ほどの小屋を建て、問谷製作所は産声を上げました。
はじめはメーカーの下請けで、ライター部品の金型づくりからスタート。
その後、プレスも手がけるようになり、商社からの依頼で引き出しのノブなど、
輸出金物雑貨の製造で売上を伸ばしました。あるとき、以前お付き合いのあった三菱重工から相談があるといわれます。
「トラック部品を試作してほしい。あなたの技術ならできるはずだ」
これが、当社の将来を決定づけた、キャブオーバー型トラックとの出会いでした。当時はボンネット型が主流。キャブオーバー型は試作車のため非量産です。
「割に合わないし、儲かりっこない」と、ほとんどの業者は手を挙げませんでした。
しかし私は、誰もやらないからこそ価値があると考え、その要請を快諾。後に、そのトラックは評判を生み、量産されることが決定しました。
金型にくわしいから、プレスの仕事も発注される。さらに溶接、機械加工、塗装と提供できる技術を広げていきました。
高度経済成長の追い風もあって、右肩上がりで売上を伸ばし、
問谷製作所はトラック用厚物大型部品メーカーとして、大きく成長したのです。 -
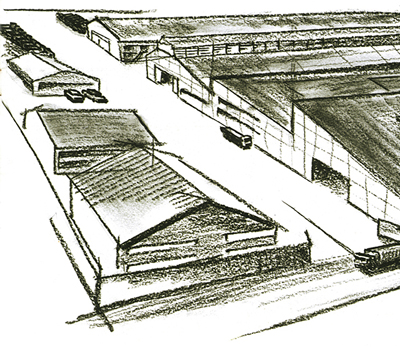
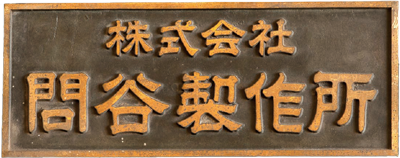
設立当初、本社と茨城工場に掲げられた看板 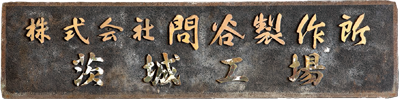
困難な課題に挑む情熱は、成長への近道である。
-
騒音・振動問題から茨城に工場を新設。
三菱との信頼を深め、ラインナップが充実。部品の受注は順調に増え、目黒から横浜へと生産設備を拡大。
さらに、今後の展開を視野に入れ、茨城工場を新設することになりました。ところが操業を開始すると、前年に起きた第一次オイルショックにより不況に。
メインバンクの横浜銀行の支援もあり、ようやく不況から立ち直ると、
三菱自動車工業からの部品の発注が、一気に増えていきました。当社はもともと、中型・大型トラックの部品をつくっていましたが、
水島製作所からの移管により、小型トラック部品も手がけるようになります。数年ごと、モデルチェンジによる更新やバリエーションの追加が発生する。
しかも、従来扱ってきた部品のほか、移管により受注したハウジング、
当社の生産技術を駆使した国内初のアルミ製エアタンクなど、
重要保安部品を中心に、次々と発生するプロジェクトの課題を一つずつ克服。「やってできないことはない」の熱意で、ラインナップを拡充しました。
忙しすぎて昼夜の二直勤務でも生産が追いつかず、毎年40~50名を採用。フォルムと社名を一新したのは、認知度と採用力を高めるねらいもありました。
茨城工場の拡張とともに、売上と組織の規模は大きく成長していったのです。 -

国内初のアルミ製エアタンク 
第3工場を新設し、製造したハウジング
逆境に立ち向かう勇気と、あきらめない克己心。
-
会社創立以来、最大のピンチを救った戦略は
新規取引先の拡大と生産部門の集約化。21世紀を目前にひかえ、当社の経営を揺るがす事態が発生しました。
バブル崩壊による不況と、お取引先様のリコール問題です。売上は最盛期から半減。これまでの拡大路線を見直すことになりました。
悩んだ末に出した結論は、営業開発部門を中心に取引先を増やすこと。
生産部門の茨城工場への集約化により、固定費を削減することの2つでした。プレス工業からはいすゞ自動車・日野自動車向け部品を、
日産ライトトラックより開発製造を受注。
カルマン社からは日産自動車向け機能部品製造を、
エフテック社より本田技研工業向け足回り部品のプレス加工を、
日本フルハーフからはウイング用、サスペンション部品など、次々と受注しました。多品種少量製品を、開発から組立までトータルラインで提供する。
その強みを活かすためISOを認証取得した結果、新規取引先が増加。
プレス工業からは重要部品の製造を依頼され、今も継続受注しています。また、構想から20年を費やした茨城工場への集約化により、生産性は大きく向上しました。
『一人ひとりが “ものづくり” の原点を見つめ、働きがい生きがいのある職場をつくる』
当社創立からのDNAは、いまも社員一人ひとりの心に息づいています。
-

プレス工業から受注したVC60 CAB RRとVC60 FLOATING